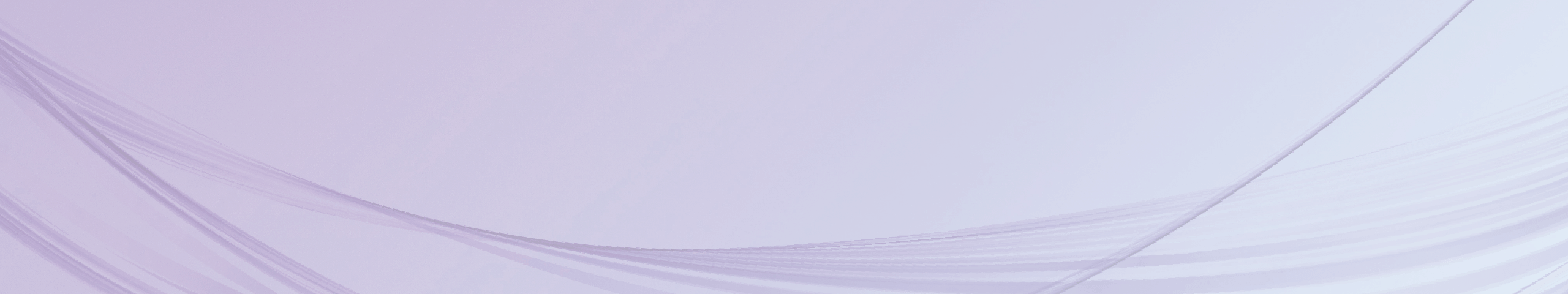今回は産後のピラティスプログラムについて解説します。
産前産後の経験は、女性の体に大きな影響を及ぼします。また、体だけではなく、気持ちの面でも大きな変化を伴います。
妊娠によって起こる心身の変化を学び、産前産後期のクライアントに対し体と心の両面から有益なサポートを提供できるように目指しましょう。
マトレセンスとは?
産後ピラティスの役割
産後ピラティスの役割は、新米ママが母親としての身体的、精神的、感情的な課題に対処できるように手助けする役割を担っています。
妊娠による姿勢の変化まとめ
・研究によると、妊娠中に75%が腰椎前弯が減少し(平坦になる)、腰仙関節と骨盤に体重がかかり、25%が腰椎が前弯し、腰椎、椎間関節、椎間板に体重がかかる。
・重心は土踏まずではなくかかと寄りに変化する。
・産後9ヶ月まで靭帯弛緩が続く。
↓
ニュートラルの再教育とコアの安定性の改善、固有受容感覚の意識を改善するエクササイズが有効。

妊娠による姿勢の変化は、下記のようになっています!
腰椎前弯が減少‥75%
腰椎が前弯‥25%
この結果からわかることは、意外にも腰椎前湾より減少する人が多いということ。
クラスへの復帰
- 一般のクラスへ戻るのは4〜6週間かかる。
- 6週間で復帰できるお母さんもいれば、もっと長く時間が必要なお母さんもいる。妊娠期間中の運動や健康の経過、どのような陣痛と出産だったかを考慮しなくてはならない。
- 帝王切開か、経膣分娩か裂傷・切開の程度など医療介入がどのくらいあったかによって変わる。
帝王切開の場合
・12週間で運動の許可が出る可能性。
・5ヶ月間はカールアップ系のエクササイズは禁止。ただし、それまで全く腹筋を使わないのではなく、腹筋のスタビリティトレーニングを行い少しづつ準備していく。
産後クラスで重要な要素
産後のクラスを構成する時に意識したいことです。
- リラクゼーションスキル
- アライメント
静的、動的アライメントのチェック。動的アライメントは脊柱全体をバランス良く動かせるか。 - 呼吸
ラテラル胸式呼吸。 - センタリング
動きの中でコントロールしながらコアを使うこと。 - 骨盤底筋
骨盤底筋に特化した、骨盤底筋だけを意識するエクササイズ。※最終的に骨盤底筋は意識しなくても働くようになるのが理想。 - 骨盤の安定性の獲得
- 上位交差性症候群を改善するためのエクササイズ
特に肩関節をしっかりと動かすこと。
母乳育児
母乳育児について知っておきたい知識です。
1. ホルモンの変化
母乳育児を続けると、プロラクチンレベルが上昇し、エストロゲンレベルが減少します。
これは、関節が脆弱になり、筋肉も弱くなっていることを意味します。
この状態は閉経の症状と似ています。
エストロゲンは骨や筋肉の維持、関節の安定に重要な役割を果たしています。母乳育児中は排卵が抑制されるため、エストロゲン分泌が低下し、閉経期と似たホルモン環境になります。
参考文献:Sims ST, Heather AK. Exerc Sport Sci Rev, 2010.
2. 骨密度の変化
母乳育児を行う最初の3ヶ月で骨密度が約5%減少すると報告されています。
ただし、この骨密度の減少は一時的なものであり、母乳育児をやめてから6ヶ月以内に回復します。
様々な場所をターゲットにした様々な体重負荷運動を加えることや抵抗運動が、骨密度低下を最小限に抑え、骨を構築するのに役立ちます。
骨密度の減少はカルシウムが乳汁に利用されることが関係していますが、通常は授乳終了後に回復が見られるため、長期的に骨粗鬆症のリスクが高まるわけではないとされています。
参考文献:Kalkwarf HJ et al. N Engl J Med, 1997.
3. 水分の必要性
母乳の約87%は水分で構成されています。
そのため、母乳育児を行っている時期は、通常より多くの水分を摂取する必要があります。
米国医学研究所(Institute of Medicine)の指針では、授乳中の女性は1日あたり約2.7〜3.0Lの水分摂取が推奨されています(食事からの水分も含む)。母乳の分泌や体調維持のためにも、水分摂取は非常に重要です。
参考文献:Institute of Medicine, Dietary Reference Intakes for Water, 2005.
その他問題となること
その他に問題となる体の変化についてです。
足底腱膜炎(そくていけんまくえん)
足の裏の土踏まずを支える腱膜に炎症が起こる状態です。
妊娠や産後は体重の増加やホルモンの影響で足のアーチが崩れやすく、負担がかかりやすくなります。
長時間の立位や歩行でかかとの痛みが出るのが特徴です。
足首の弛緩性(しかんせい)
妊娠・産後はリラキシンというホルモンの影響で靭帯がゆるみやすくなります。
足首の靭帯が安定しにくくなるため、ねんざや関節の不安定感が起こりやすくなります。
産後しばらくは足首のぐらつきが残る方もいます。
膝の問題(特に内側広筋との関係)
膝の不安定さや痛みは産後に多い訴えです。
- 内側広筋(大腿四頭筋の一部)は膝を安定させる重要な筋肉ですが、妊娠・産後は弱くなりやすいです。
- 膝関節に過度な圧迫をかける動き(深いしゃがみ込みなど)は避けた方がよいです。
- 膝を大きく屈曲・伸展する動作を繰り返すと炎症や痛みにつながりやすいです。
乳腺炎(にゅうせんえん)
母乳を作る乳腺に炎症が起こる状態です。
母乳の通り道が詰まったり、細菌感染が原因になることがあります。
発熱や胸の痛み・腫れを伴うことがあり、安静や授乳方法の改善、場合によっては医療的治療が必要になります。
静脈瘤(じょうみゃくりゅう)
血液が心臓に戻りにくくなり、下肢の静脈がふくらんで浮き出る状態です。
妊娠中は子宮により血流が圧迫されることや、ホルモンの影響で血管が拡張しやすくなることが原因です。
ふくらはぎや太ももに多く見られ、長時間の立位で悪化しやすいです。
手根管症候群(しゅこんかんしょうこうぐん)
手首の中を通る神経(正中神経)が圧迫され、手のしびれや痛みが出る症状です。
妊娠や産後は体液がたまりやすく、手首の腱鞘が腫れて神経を圧迫しやすくなります。
特に夜間や朝方にしびれや痛みが強くなることがあります。
まとめ

産前産後はホルモンの影響や体の変化により、関節の不安定さ、炎症、血流や神経の圧迫による症状が出やすくなります。
これらの特徴を理解しておくことが、トレーナーとして安全で効果的なサポートを行うために重要です!
骨盤底の回復
産前産後で最も影響を受ける骨盤底についての知識を学び、実際のトレーニングに結びつけましょう。
骨盤底は二層構造(骨盤隔膜と尿生殖隔膜)
骨盤底は 骨盤隔膜(pelvic diaphragm) と 尿生殖隔膜(urogenital diaphragm) の二層構造を持っています。
- 骨盤隔膜:深層にあり、膀胱・子宮・直腸などの臓器を下から支える重要な層です。
- 尿生殖隔膜:浅層にあり、尿道や外陰部の支持やコントロールに関わります。
後ろから前に「引き締める」ように収縮させると、骨盤隔膜の深層にある 尾骨筋 や 肛門挙筋 といった筋肉をターゲットにできます。
図:骨盤底筋の位置関係(骨盤隔膜・尿生殖隔膜)
筋線維の比率:遅筋繊維と速筋繊維
骨盤底筋は 70%が遅筋線維(タイプI)、30%が速筋線維(タイプII) で構成されています。
- 遅筋線維:持久力に優れ、長時間の収縮を支える役割を担います。
- 速筋線維:瞬間的な力発揮や急な収縮に対応します。
そのため、骨盤底筋を強化するためには、両方のタイプを意識して使うことが大切です。
図:骨盤底筋群(遅筋と速筋が混在する)
リリース(弛緩)も大切
骨盤底筋は「締める」ことだけが重要ではなく、リラックスしてゆるめられることも同じくらい大切です。
常に緊張していると血流が悪くなり、痛みや不快感につながることがあります。
まとめ

骨盤底筋は二層構造を持ち、深層の筋肉(肛門挙筋・尾骨筋など)を引き締めることで鍛えることができます。
また、70%が遅筋、30%が速筋で構成されているため、両方にアプローチすることが重要です。
さらに、「締める」だけでなく「ゆるめる(リリース)」ことも、健康な機能を保つために欠かせません。
産後期に推奨される骨盤底エクササイズ
骨盤底エクササイズは、産後尿を出したらすぐに始められます。
骨盤底エクササイズを行う際に意識するポイントは、以下の通りです。
- 良いアライメントと呼吸の併用が大事。
- 臀部や腹直筋、腹斜筋を緊張させない。
- 吐く時に骨盤底をリラックスさせる。
腹直筋離開
腹直筋離開(ふくちょくきんりかい)とは、妊娠や出産などによって お腹の真ん中にある結合組織(白線:はくせん)が引き伸ばされ、 左右の腹直筋が離れてしまう状態のことをいいます。
妊娠中にお腹が大きくなると、胎児を包むために腹壁が前方へ広がり、 腹直筋の間をつないでいる白線に強い張力がかかります。 これにより、腹直筋が左右に引き離され、真ん中の部分が薄く・弱くなってしまいます。
出産後もすぐには元に戻らず、特に産後初期はおへそ周囲にすき間(1〜3cm程度)が残ることがあります。 この離開自体は自然な現象ですが、体幹の安定性の低下、腰痛、姿勢の崩れなどにつながることもあるため、 適切な回復エクササイズが大切です。
腹直筋離開の重要なポイント
現在は、どのくらい離開があるかよりも、その下や周囲の筋肉の緊張度の方が重要とされています。
ただし、離開の程度によって行えるエクササイズは変わります。
また、エクササイズ中におへそ周囲が半球状に盛り上がる「ドーミング(abdominal doming)」が見られる場合もあります。
腹直筋離開が回復するまでには、産後およそ一年程度かかるといわれています。初期の段階では強い腹筋運動は避け、少しずつ段階を踏んで発展させていくことが大切です。
ドーミング(abdominal doming) とは、腹圧をうまくコントロールできず、腹直筋の隙間から内部の組織が押し出されて見える現象です。
この状態を腹筋で抑え込むことができない場合、結合組織や腹壁に過剰な負担がかかるため特に注意が必要です。
改善に向けた基本手順
腹直筋離開がある場合、腹筋の健全性を改善するためには、次のような手順で進めていきます。
- 腹横筋のアイソメトリックエクササイズ
- ペルビックティルト
- 緩やかなカールアップ(始めのうちは腹壁が広がらないように気をつけて行います)
腹直筋離開の検査方法
腹直筋離開は、カールアップ動作で確認します。
- 仰向けになり、膝を立てます。
- 片手の指を横方向に3本揃えて当てます。
- おへその上、中心、下と位置を変えて、隙間をチェックします。
※このテストは産後3日以上経ってから行うようにしましょう。
改善の経過
腹直筋離開の改善には、およそ1年から18か月かかります。
離開がある間に、腹腔内圧を高める強い腹筋運動を行うと、離開が悪化したりヘルニアを形成するリスクもあります。
そのため、無理をせず、少しずつ改善していくことが大切です。
回復の目安
産後8週までには、離開はおへその位置で約2cm幅まで閉じるのが通常です。
妊娠前の状態に完全に戻るわけではなく、約1.5〜2cmの隙間が残るのが自然な状態です。
ですが、腹直筋をつなぐ「白線(linea alba)」の状態は改善し、張りと安定性が戻っていきます。
腹直筋離開の改善における最終的なゴールは、
・腰椎や骨盤の安定性を回復させる
・腹直筋を短く、強く機能させる
こと。これにより、体幹全体の安定性や日常動作の安全性が高まります。
腹直筋が回復するまで避けるエクササイズ
腹直筋が回復するまで、以下のようなエクササイズは避けましょう。
- 腹腔内圧を高める体幹屈曲を伴うエクササイズ
例)ロールアップ、ハンドレッド、ダブルレッグストレッチなど - 腹筋をストレッチするもの、スタビリティボールなど不安定になるイクイップメントを使うもの、腹斜筋や腹筋を強く使うものは避ける
例)ローリングライクアボール、クリスクロス、スワン等 - オープンキネティックチェーンの状態で行われる脊柱回旋・屈曲を伴うエクササイズ
例)ストマックコントロールツイスト、ティルト、アンナバンツイスト等 - 四つん這いポジションのエクササイズは始めは手足をつけたままスタートし、手足を床から離すのはコアの安定性が回復してから
- 膝を伸ばした状態で行うプランクスタイルのエクササイズ
推奨されるエクササイズ
- 四つ這い含む全てのポジションでのアイソメトリック収縮
- 骨盤を安定させたまま手足をバラバラに、多方に動かすエクササイズ
- メディスンボールを使ったエクササイズ
- ペルビックティルトやスパインカール
発展
複斜筋を意識するために両手にバンドの抵抗を加える
さらに発展
片手、片足でバンドの片側を引っ張る
腹直筋離開がある場合の発展
タオルを巻いたカールアップ、オブリークカール
骨盤帯痛(PGP)について
骨盤帯痛(PGP)は、骨盤に関するさまざまな問題をまとめた総称です。
骨盤は前後をつなぐ「輪」のような構造をしているため、後部骨盤に機能障害があると、前部の骨盤にも問題が生じることが多いとされています。
PGPが疑われる場合や強い痛みがある場合は、理学療法士や医師に相談するようにアドバイスしましょう。
恥骨結合の機能不全について
恥骨結合は、フォース・クロージャー(force closure) の影響を受けます。
フォース・クロージャーとは、仙腸関節を安定させる仕組みの一つで、筋肉や筋膜の張力によって関節を安定化させる機構を指します。具体的には、胸腰筋膜でつながる大殿筋、ハムストリングス、内転筋群、腹斜筋群などが連動し、骨盤の左右を結ぶ恥骨結合や仙腸関節に安定性をもたらします。
この仕組みが適切に働くことで、恥骨結合にかかる負担を軽減し、産前産後に多い骨盤帯痛(PGP)や恥骨痛のリスクを抑えることにつながります。
仙腸関節の痛み
仙腸関節の痛みは、対処しないまま放置すると悪化し、長期的な問題につながることがあります。
左右非対称な動き、マーメイドやあぐらで座るような姿勢は避けることが大切です。
骨盤帯痛がある場合のエクササイズを再開してからの注意点
- 脚を開く動きや内転筋の使用は徐々に行う
両脚を開閉する動作は負担になりやすいため、初期は両足を閉じて行うなど、安定した姿勢から始めます。 - 左右対称のエクササイズから始める
エクササイズだけでなく、日常生活でも左右差のない動きを意識します。
例:ベッドから降りるときは片足から立ち上がるのではなく、両足をそろえて降りる。 - 膝を曲げて行う姿勢から開始する
側臥位でも仰臥位でも、膝を曲げて安定させて行います。側臥位では膝の間にクッションを挟み、左右対称に保つと負担を軽減できます。 - 体幹と股関節周囲の安定筋を使う
動きながら多裂筋や腹横筋を意識したり、ブリッジ動作でバンドを巻きコアと外転筋を同時に鍛えるなど。 - 側臥位で行うエクササイズや立位・座位での回旋動作
特に、負荷をかけた回旋は症状を悪化させる可能性があるため禁止とします。
尾骨の痛み
出産時には、尾骨にあざや炎症が起こる場合があります。
エクササイズを行う時の注意点
- ロールバック(ロールダウン)のような動きは行わない。
- 骨盤を後傾させる前屈みの姿勢を避ける。
前屈みではなく、坐骨でしっかり座るようにサポートしましょう。
産後ピラティスプログラムの主な目的のまとめ
産後ピラティスを目的としたプログラム作成において、意識することです。
環境と心身のサポート
- 安全で協力的な環境を用意すること
- お母さんがリラックスし、自分の時間を持つためのお手伝いをすること
姿勢・感覚・呼吸
- 姿勢に対する意識と固有受容感覚を高めること
- 呼吸を改善し、胸郭の動きを整えること
骨盤・体幹の回復
- 骨盤底筋のリリースと、遅筋・速筋繊維の働きを改善すること
- 腹直筋離開の改善を促すこと
- 骨盤の安定をサポートすること
胸郭を含む上半身の調整
- 胸を開き、肩や首まわりの緊張を解くこと
- 頭・首・肩の正しいアライメントを指導すること
- 広がった胸郭を元に戻し、複斜筋をアイソメトリックに働かせること
脊柱の機能改善
- 脊柱の伸展を促すこと
- 胸椎の回旋や伸展を取り入れること
- 腰椎の屈曲と股関節の可動性を高めること
下半身の強化と柔軟性の回復
- 臀筋の強化
- 穏やかにハムストリングスや股関節屈筋をストレッチすること
- 足裏の内在筋を強化すること
全身の機能回復
- バランスとコーディネーションを回復させること
産後セッション計画
バランスの取れた産後のセッションプログラムを組み立てるために意識することを、準備パート→メインパート→最終パートに分けて説明します。
準備パート
- 基礎的な体の使い方を思い出す
- 良いアライメントを習得する
- 胸式ラテラル呼吸、深い腹式呼吸、「シーッ」と息を吐く胸郭を意識した呼吸を行う
- 骨盤底を意識し、深層のコアとのつながりを修正する
- 関節を優しく動かす(例:一つの関節につき二方向に動かす)
- 骨盤安定のためのエクササイズ
メインパート
- 腹筋の健全性を回復させるエクササイズを取り入れる
- 骨盤底エクササイズを組み込む
- 脊柱を全ての面で動かす(屈曲・伸展・回旋・側屈)
※母乳育児中は胸が張りやすいため、伸展系の動きはセッションの早い段階で取り入れる - スクワットとバリエーション
- バランスとコーディネーションのエクササイズ(例:二つ以上の関節を同時に動かす、複数動作を組み合わせる)
- 足と足首の動きを整えるエクササイズ
- 上半身と下半身の動きのバランスをとるエクササイズ
最終パート
- 緊張を解放するための呼吸
- リラクゼーション
- 骨盤底のコントロール(立位や膝立ちなど、骨盤底に負荷がかかる姿勢で行えると効果的)
- 良い姿勢への意識を確認する
- 最後は立位で終える
- 立位の後に足首や足趾のエクササイズを取り入れるのもおすすめ
産後プログラム事例
通常クライアント
準備段階:
- リラクゼーションポジションでのラテラル胸式呼吸
- 〃 骨盤底筋エクササイズ(エレベーター、wind zip、フラワーなど)
- ウインドウズ
- シングルショルダードロップヘッドオンボールウィズリーチ
- ニーフォールド→ニーフォールド&アダクトに発展させる
メイン段階:
- ニーオープニング→ニーオープニングフットオンボール
- ペルビックスタビリティフィートオンボールアームスレイズド
- ダート
- オイスター
- フロント&バック ショートレベルズ
- ハイニーリングウエストツイスト
最終段階:
- ハムストリングスストレッチ
- ウォールスライドヒールリフト
- サイドリーチ
- トーズ(立位で)
- 立位での胸式呼吸
骨盤帯痛があるクライアント
準備段階:
- リラクゼーションポジションでのアライメント調整
- リラクゼーションポジションでの6つの呼吸
- ニーリングポジションで前傾での骨盤底筋リリース(wind zip、エスカレーター、ナックなど)
- ダブルショルダードロップス
- ピロースクイーズ
メイン段階:
- ペルビックティルト
- スパインカール→スパインカールウィズバンドに発展
- ダイアモンドプレス
- ダート
- 4ポイントニーリングテーブルトップ(産後6週間以降)
- レッグスアップウォールポイント&フレックス
- レッグスアップウォールトークリーピング
最終段階:
- スクワット
- ウォーキングザアーチズ
- 立位での呼吸、ロールダウン
腹直筋離開のあるクライアント
準備段階:
- スカーフ バンドブリージング
- 椅子に座った骨盤底筋エクササイズ(wind zip、エスカレーター、ナックなど)
- シングル&ダブルショルダードロップス
- ビッグスクイーズ
- リブケージクロージャー
メイン段階:
- リブケージクロージャー
- ペルビックスタビリティレッグスライド
- 〃ニーオープニングス→オンボールに発展
- ペルビスオンボールニーフォールド
- ペルビスオンボールビラテラルバンドプル→+レッグスライドに発展させる
- フロント&バック ショートレベルズ
- ヒップフレクサーストレッチオンボール
最終段階:
- リブケージクロージャーウィズレッグスライド(骨盤の安定性が得られてから)
- スクワットウィズヒールレイズ
- スクワットウォーキング

産後エクササイズ指導は、出産後のママの心と身体の両方をケアする大切な機会になります。
インストラクターとして、ママが安心してエクササイズに取り組める環境をつくりながら、正しい知識とあたたかいサポートで体の回復をお手伝いしましょう!